こんにちわ!ショウです。
いろんなダイエットを試しているけど効果が全くなかったなんてことありませんか?
どんなダイエットをしたとしても結局どれくらいのカロリーをとったかで決まってくるのです。
例えばご飯を食べる前にきゅうりを食べるとか、サラダを先に食べるとかそれも結局満腹感を満たしてその後に食べる量を減らしてるだけなんですね。
最終的にはやっぱりカロリーなんです。
なので今回はどれくらいのカロリーをとればいいのか何を食べればいいのかを解説します!
【結論】カロリー計算ができていれば迷うことはない

いろんなダイエット法がありますがほとんどの場合体重が落ちなかった時に原因がわかりづらいことがあります。
これを食べたら痩せると言われたけども全然痩せなかったとか、運動していたけど痩せなかったとか。
その1番基本にあるのがカロリーです。
低カロリー食材を食べたからといってそれをたくさん食べたらカロリーは上がります。
いくら運動をしたからといってそれ以上にカロリーをとっていては痩せません。
だからカロリー計算はやっておいた方がいいんですね。
ということでここからはそのカロリー計算の方法と考え方について解説していきます。
①:体脂肪を落とすための摂取カロリーとは
②:ダイエットにおいて大切なのは脂肪を落とすこと
僕も最初は訳がわからなかったですがちょっとづつ学んでいきました。
やっていくうちに計算も慣れていくのでまずは始めることですね。
①:体脂肪を落とすための摂取カロリーとは
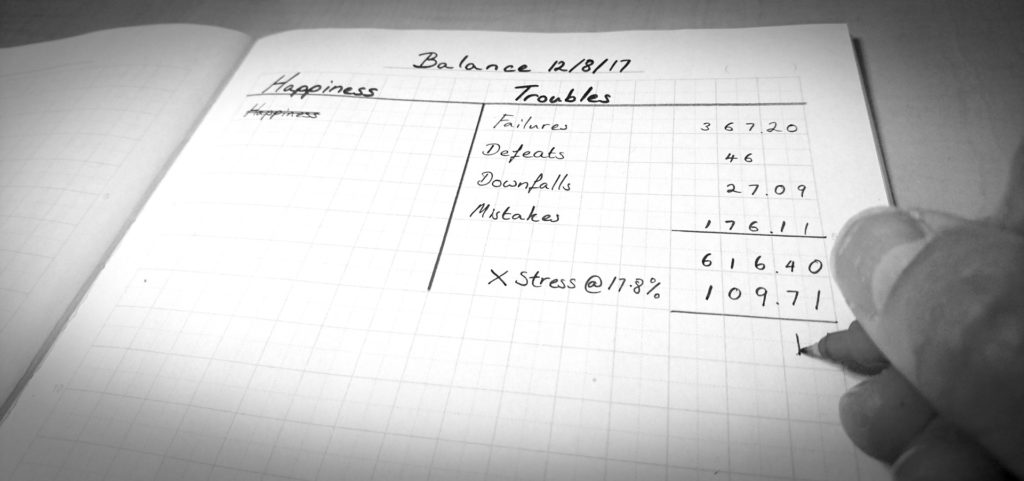
一言で言うと 摂取<消費 にすればいいんです!
例えば 摂取 < 消費
1500kcalー1800kcal=ー300kcal
このー300kcalを積み重ねていけば脂肪は落ちていきます。
脂肪を1キロ落とすには約7000kcal消費しなければならないと言われているので単純計算この生活を23日間続ければ脂肪は1キロ落ちるわけです。
まぁそう簡単にはいかないんですけどね笑
じゃあどうすればうまくいくのか?
何を食べればいいのか?
そしてダイエットにおいていちばん勘違いしてはいけないのが体重を落とすのではなく脂肪を落とすことを考えていきましょう。
②:ダイエットにおいて大切なのは脂肪を落とすこと

よくみなさんが勘違いしているのが体重を落とそうとしていることです。
ダイエットをする理由はそれぞれあると思いますが一緒に筋肉を落としてしまうのはよくありません。
ではどうすれば脂肪のみを落とすことができるのか?
それはPFCバランスを意識することです。
PFCバランスとは
P=タンパク質
F=脂質
C=糖質
それぞれをどれくらいの量取るかが大事になってきます。
例を出します。
1日1500kcal摂取する場合
P=30%=450kcal=112g (タンパク質1g=4kcal)
F=20%=300kcal=33g (脂質1g=9kcal)
C=50%=750kcal=187g (糖質1g=4kcal)
こんな感じになります。ごめんなさいかなりわかりづらいですね。
正確にこの数字でなければいけないわけではないので大体で大丈夫です。
僕もこの計算でやってみて最初はかなりめんどくさかったですがちゃんと体脂肪は落ちていきました。
だんだん何がどれくらいのカロリーあるとか自然とわかってきます。
今ダイエットが停滞期に入っていると言う人はやってみるといいかもしれません。
僕が使っている食品のカロリー計算をしてくれるサイトです。
もしよろしければ使ってみて下さい!
https://calorie.slism.jp ←カロリーslism
・まとめ
基本的にはこのカロリー計算をしてからいろんなダイエットに挑戦した方がいいと思います。
それでも落ちない時もあります。
そう言う時はもう一度自分の摂取カロリーを見直してみるといいかもしれません。
どんなに体重がが落ちなくても必ず他に方法があるので一緒に頑張りましょう!
僕も毎日ダイエットについて研究しているので一緒に頑張りましょう!
質問はインスタやTwitterのDMからお願いします。
それでは!!
個人的オススメ記事
【痩せるのは最初だけ】糖質制限から始めるダイエットが危険な理由【経験者が語る】
【イライラ】ダイエット中にどうしても食べたいものがある時の対処法【モチベ】
【失敗】ダイエットをしているけど何回もリバウンドを繰り返してしまう【無限ループ】
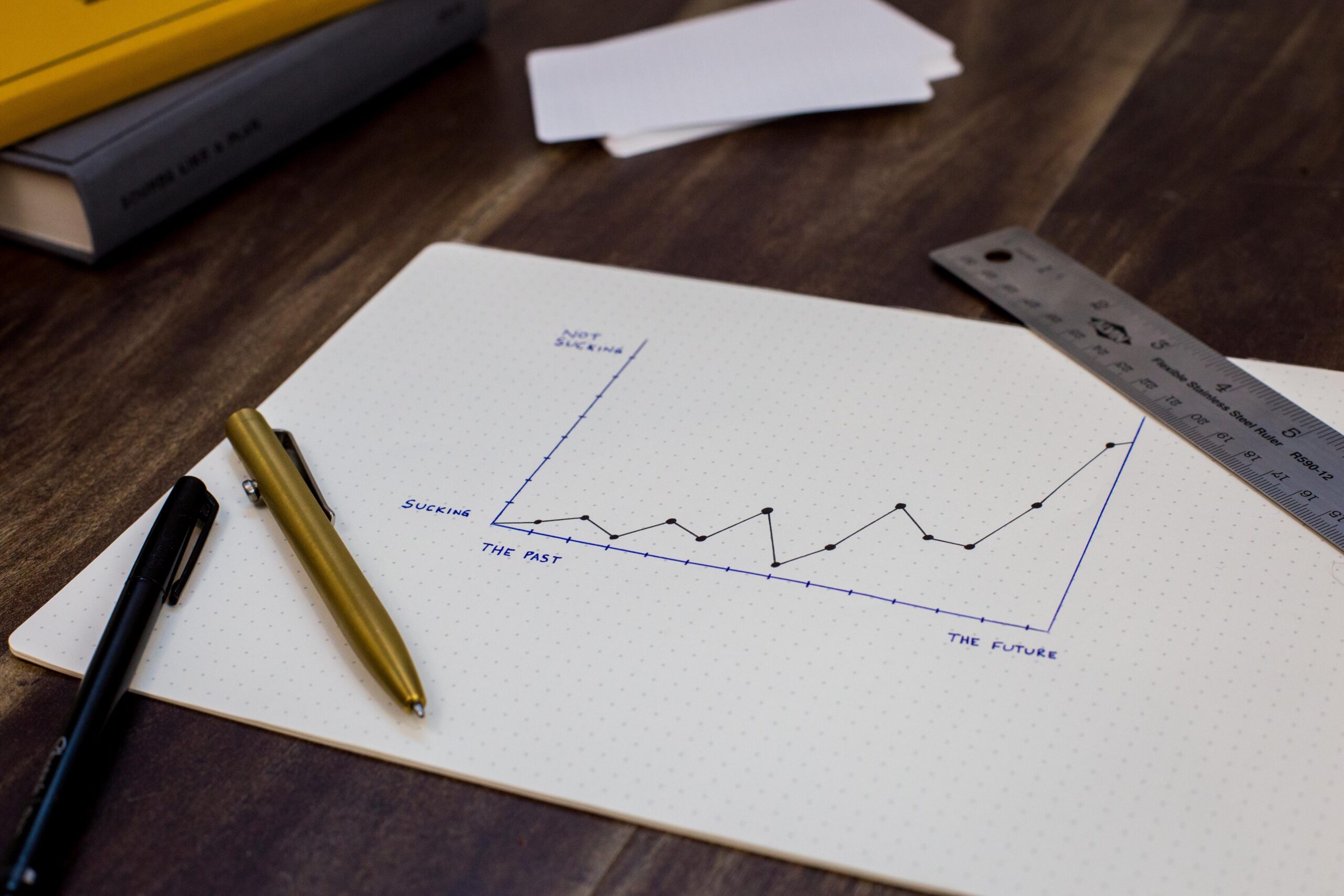


コメント
[…] ダイエットは結局はカロリー計算 […]
[…] ダイエットは結局はカロリー計算 […]
[…] ダイエットは結局はカロリー計算 […]